
声なき刀が語るもの──小説『刀が泣くとき、探偵は声をきく』
- Emi | Kenshirou Siba Labo

- 2025年4月29日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年5月3日
──名を持たぬ刃が、命を喰らう。
それを聞くのは、声をきく探偵――片桐透馬。
刀は、叫ばない。けれど命の声は、確かにここにある
今年は、今までやったことないことに挑戦しようと思っていた。
それで、ふと思いついて、ミステリー小説を書いてみた。
“オカルトに寄りすぎない”伝奇✖️異能✖️刀剣✖️ミステリー。
最後まで書いたけど、今絶賛見直し中!
小説『刀が泣くとき、探偵は声をきく』とは
刀は武器じゃない。
ただそこに置かれ、
誰にも触れられずに、
それでも、声を持っていた。
書きながら、私は何度も「静かだな」と思った。
殺人もある。血も流れる。狂気も潜む。けれどこの物語には、叫びがない。
声があるのに、叫びがない。
むしろ「聞こえない声」が物語の中心にある。
でも、いろいろ追記をしているので、公開するときには叫びまくっている可能性はある(笑)
“聞こえる”という宿命

主人公の片桐透馬は、“刀の声”が聞こえる元刑事。
声といっても、明瞭な言葉ではない。
鉄の冷たさに宿った祈り。
打たれた瞬間の痛み。
誰かの「生きてほしい」と大切な人を守りたいという、どうしようもない願い。
それらが、「声」として透馬の中に入ってくる。
彼はそれに傷つき、惑い、ときに拒む。
けれど、逃げきれない。
“聞こえる”というのは、選べないことだから。
刀に宿る祈りと、命のかけら
作品の中には、何度も“命”という言葉が出てくる。
命のある刀。命のない刀。
魂と、祈りと、記憶と。
(書いている自分もややこしいなぁと思ったが、なぜかそういう話になった。)
それらの境界はとてもあいまいで、でも確かに違うと、作中の登場人物たちは知っている。
ある刀は、誰かの願いとともに生まれた。
「帰ってきてほしい」
「守ってほしい」
「忘れたくない」
そういう祈りが、刃に命を宿らせる。
鏡という男の痛み

一方で、鏡という男は、声なき命を“創ろう”とする。
死んだ魂をなぞるのではなく、喰らわせて、歪んだ命を打ち出そうとする。
その姿は恐ろしくて、どこか哀しい。
「泣かせるには、汚しが要る」
そう言いながら彼が打つ刀は、祈りではなく、痛みのかたまりのようだった。
書いていて嫌いになれない男でした。
白犬と黒猫が導く“応え”という選択

そしてもう一つ、白犬のシロと、黒猫のクロ。
二匹は普通の犬と猫の時もあるし、人型の時もある。
彼らは現実にも夢にもふと現れて、透馬を導く。
「選ばれたんじゃない。“応えた”のよ」
その言葉が、透馬の成長と、物語の底にあるテーマを象徴している気がした。
当初、透馬は聞こえるということから逃げている、どうしようもないヘタレだったので、この言葉には、
「あぁ、透馬、立派になって・・・」と、なんだか感慨深いものがありました(笑)
それでも祈りは、確かにここにある
誰かに見つけられるのを待つ命。
言葉にされない祈り。
それを“応える”という形で受けとめていくこと。
それが、生きるということなのかもしれない。
読む人によって、きっとこの物語の“声の聞こえ方”は違う。
でも、もしあなたが今、
どこか心の奥で何かを失ったような気がしていたなら——
『刀が泣くとき、探偵は声をきく』の静かな祈りは、きっと届くかもしれない。
読後に、きっと耳を澄ませたくなる。
あなたのそばにある“声なきもの”の祈りに。
それは叫ばないけれど、
確かにここにある、命の音だから。
見直しが終わったら、ちゃんと公開します。
あらすじ
都市の片隅で、“名を持たぬ刀”による異常な事件が続発する。
誰にも聞こえないはずの声を聞き、刃の問いに向き合う探偵・片桐透馬。
怪盗「鏡」が遺した未解明の“再現刀”をめぐり、祈り、模倣、崇拝、狂信が広がっていく。
名を与えるとは、命に応えること。
声を持たなかった者たちの記録を、彼は“人間として”引き受ける。
これは、誰にも届かなかった声と、それに名を返す者の物語。


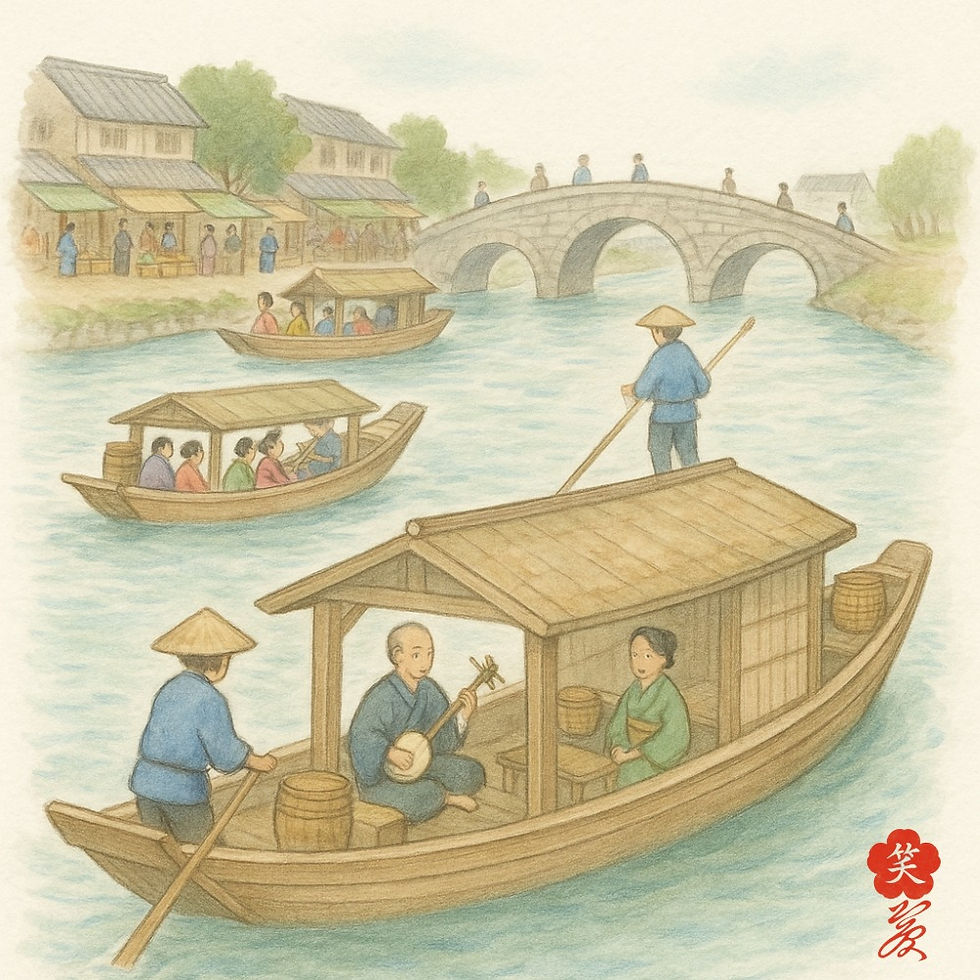

コメント